




ガチャ
少し頼りなさげな扉の取っ手に手をかけ店内に入ると、そこは喫茶店のようであり、カフェのようでもある店。足下に目をやると、三和土(たたき)と板張りとカーペットとが寄り合い、少し不思議な空間を下から支えている。
青い。
一面が青いわけではないのだけど、カウンターの背、壁、メニューブックなど、藍の青の存在感があって、それがお店全体の第一印象につながっている。
階段がある。壁沿いには本が所狭しと並び、2階へと向かおうとする足を引き留める。登り切ると、広いフラットな空間にオレンジ色の光が射し込んでいた……。
![]()
西国分寺の駅前に育った1本の「くるみの木」が
となりまちに種を落とすようにして
2017年3月27日、胡桃堂喫茶店はオープンしました。
西洋というよりは東洋
日本、国分寺、ぼくら自身
あるいは喫茶店という文化など
ぼくらの足下にあるいいものに目を向け
それらに根ざした形で
未来へとつながるぼくらの仕事をつくる
そんな思いで店づくりを始めました。
藍で染めた和紙で店内を飾り
かつて100年前の喫茶店に
置かれていたのではないかというような家具類
日々、だしを取り、あんこを炊き
地元の豆腐屋さんで豆腐を買い
5月には、新茶とよもぎのお餅をメニューに。
さらに国分寺やまわりの土地で
お米をつくるようになったことで
ぼくらの日々を取り巻く自然と
そのリズムを少しずつ共有できるようにも
なってきました。
梅雨や、しめなわを飾るといった季節の出来事も
今ではだいぶ実感として捉えられます。
そして、店に残った「余白」では
お客さんや、まちの仲間との関わりが
芽を出しつつあります。
本棚の一角で
営業時間外の店内で
畑で、まちで。
ぼくらの店には事業計画はなく
生み出したい成果が
あるわけでもありません。
1本の木が育つように
さまざまな縁や偶発性を
楽しみながら
その瞬間を全力で生き
時間をかけて
なすべき樹形を自然となしていけたらいいなと
思っています。
ようこそ、胡桃堂喫茶店へ。
![]()
店の開業時に、当時考えていたことを言葉にしたものです。時間が経って、今なら違う表現をするなというところや、考え方が少し変わった部分などもありますが、店づくりの一つの原点として残しておこうと思います。
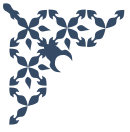
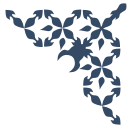
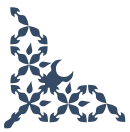
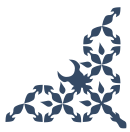
・日本、国分寺、ぼくら…、に由来のあるものごとでお店を満たしたい。長い歴史的な背景があってそうなっているもの、この間まであったはずなのにいつの間にか失われているもの、これから未来に向けて、ぼくらが誇りをもって受け継いでいきたいと思うもの。
・まずはそれらを学ぶことから。ぼくらこそ、そうした足下にある深いものの価値に気付けていないことが多いと思うから。過去から学びつつ、そこに新しい「油」を継ぎ足していくことで、未来へとつながる新しい「伝燈」を築きたい。
・古いものにこそ価値があるということでもなく、50年、100年、200年といった時間軸で考えるからこそ、ぼくらにとっての「本質的な仕事」が何なのか、指針が得られると思うから。
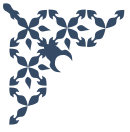
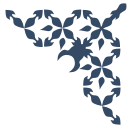
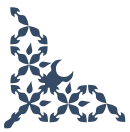
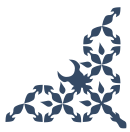
・成果へと最短距離(最小のコストと労力)で向かおうとするのならば、人間は機械にかなわない。でも最後に人の心を動かすのは、その仕事へと向けられた人の真摯な時間と手間なのだと信じている。
・時間と手間をかけた仕事が、その熱量を感じ取る心と出会えたとき初めてそこに価値が生じ、経済的に持続可能な事業ともなり得る。
・時間と手間とを要する仕事に粘り強く向き合い続けた人だけが、その先にたどり着ける境地がある。そうした境地にある熱量ある洗練こそが、ぼくらの仕事のありようの目指す先なのだと思う。
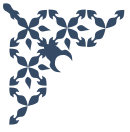
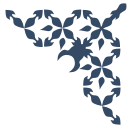
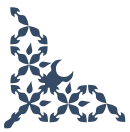
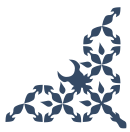
・ぼくらには、ぼくらの風土にあった暦がある。季節の楽しみ方がある。それは身体と感情とで感じ取る、生きる律動のようなもの。食事で、器で、植栽で、装飾で、本棚で、季節の移ろい、暦の節目を感じたい。
・日常(ケ)には日常の味わいがあり、非日常(ハレ)には非日常のよろこびがある。前者は倹ましく、後者は華やかに。気がつけば今は毎日がハレのよう。むしろケを整えることで、ハレはきっといっそう輝く。
・人間も、自然やいのちや世界の大きな循環を構成する一つの要素。肩肘張らなくても、その大きな流れに身をゆだねることで、進むべき道は自然と見えるはず。そしてその大いなるものに身をゆだねられたときの安心感こそ、ぼくらの帰る場所。
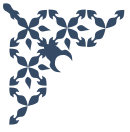
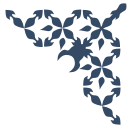
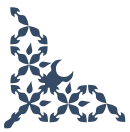
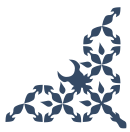
・喫茶店の果たすべきまず第一の役割は、いつもやっていること。
・喫茶店とは、ここだけ別の時間を刻むことを許された特別な空間という気がする。一人でも、誰かとでも、心落ち着けてふっとひと息。大きな時の流れに寄り添って、自分のリズムを取り戻し、自分のリズムが動き出す。来たときよりも帰りの方が自分が整い、元気になってる不思議な場所。
・空間も、メニューも、接客も、「最高級の」というより、その人らしさがあって、時間と手間とをちゃんとかけた丁寧な仕事でお迎えしたい。そうした仕事こそ、最後には信じ、愛されるものだと思うから。
・喫茶店は飲食店であるとともに、それ以上の存在でもある。帰り道、お客さんの足取りが軽く、心が健やかであるとするなら、ぼくらは医者でさえあるのかもしれない。
・なくなるとなったとき、そのことを心から惜しんでもらえるお店でありたい。
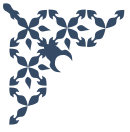
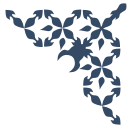
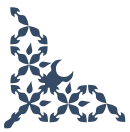
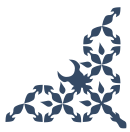
・本の世界にぼくらが入り込むのではなく、ぼくらの世界に本を招きたい。今、ここにある現実を生きるぼくらが、古今東西の賢人を招いておしゃべりするかのように。
・棚に並ぶのは、ぼくらをめぐる関係性の中にある人たちが大事にしてきた本。著者はあなたのとなりにいる人(かもしれない)。お店をめぐって起こるさまざまな状況や経験、学びが本の形へと結晶化することだってある。そうしてできあがるのは、他の誰でもなく、ぼくらにとってこそ必然性のある本棚。この地に眠る知的資源の顕在化。
・手でつくる。印刷や製本を自分たちでやる。本をつくれるようになると、本との関わり方が広がる。小冊子を束ねて自分だけの詩集をつくることもできるし、お気に入りの文庫本の仕立て直しや、大事にしてきた本の修理だって。並ぶのは湯気が立つような「できたての本たち」。
・書き手、編集者、デザイナー、印刷する人、製本する人、出版する人、届ける人、読む人がこの半径5メートルに共に会す。そのごった煮みたいな複雑系から、思いがけない出版業界の革新だって起こるかもしれない。
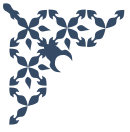
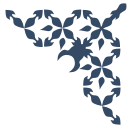
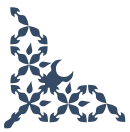
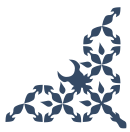
・仕事に効率を求められると、どうしても結果に向けて最短距離を進もうとする。でも仕事がお金を稼ぐための手段ではなく、誰かをよろこばせるための何かであるとするなら、そこに求められるものは整った形というより、きっと熱量。
・そのためには身体をつかって仕事をするといい。書き心地のいいペンを使うと身体がよろこんで、もっと文字を書きたくなるように。目の前に体温をもった誰がいると、その人の表情から何かを感じ取ってしまうように。身体で仕事をすると、最短距離を行きたがる脳を少しおさえて仕事に雑音が増える。その雑音が、思考の枠を広げてくれたり、アイデアに実感を伴わせてくれたり、最終的な仕事の質を高めてくれるということがきっとある。
・ここには机と、紙とエンピツと、のりとはさみと、用意します。小豆を選り分けたり、紙に向かって考えごとをしたり、製本したり、文章を書いたり、絵を描いたり。それも一人じゃなく、誰かと一緒にできるといい。そのときたまたまその場に居合わせた誰かとのやり取りが、人の人生を大きく動かすことだってあるかもしれない。
・工房は学びの場にも。他者との対話を通じて、自分に気付けたり、世界が広がったり深まったり、「真理」への見通しがよくなったり。それらに伴走してくれる本棚も、隣にある。
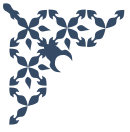
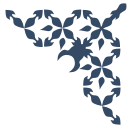
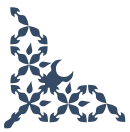
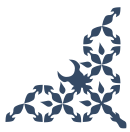
・事業計画や設計図があると、日々の営業や一つ一つの関係性はその手段になる。ぼくらはむしろ、一日一日の営業、一人一人のスタッフ、一人一人のお客さん、一杯一杯の珈琲に力を注いで、その関わりから立ち上がってくる「何か」を楽しみに待てばいい。そうした一つ一つの状況やアイデアがときに具体的な活動になり、そのうちあるものは続き、あるものは続かなくなるだろう。そして、木が枝を伸ばし、葉をつけ、花を咲かせ、実を成すように、お店が自然と、なすべき樹形をなしていくといい。
・誰かが、自らの不自由をもかえりみず、誰かを思っての仕事をする。そうした「贈る」仕事が「受け取る」人の心と出会って、感謝の気持ちを生む。そしてその感謝の気持ちはまた次の「贈る」仕事へ…。そうした交換の集積は、やがてその「場」自体に<いのち>を吹き込む。そしてその<いのち>によって、その場で働く一人一人の<いのち>がいかされる。それは土と植物の関係にも似ている。
・お店は、スタッフだけがつくるものではない。内からのエネルギーと外からのエネルギーがせめぎ合い、関わった一人一人がそこにいきるお店として育っていくといい。そうして、このお店は多くの人にとっての「自分のお店」となり、いつか開店記念日をともに祝いあえるようなお店になるといい。